 ベール
ベール皆さん、こんにちは。小学校教員をしているベールと申します。
早速ですが、皆さんは、こんなことを思った時はありませんか?
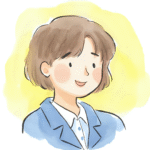
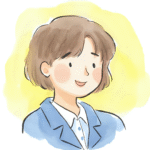
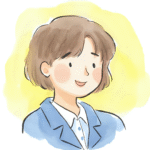
ほめることは大事だと聞いたけど、何でもかんでもほめるのはどうなの?
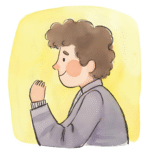
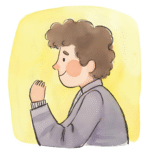
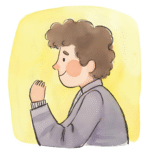
ずっと子どもを叱ってばっかり…これでいいんだろうか
「良いこと」をしたらほめる、「悪いこと」をしたら叱る。
これは、私たち大人が小さい頃から受けてきた教育であり、当たり前にも感じます。
実際に、「ダメなことはダメ」「良いことは良い」と伝えるのは、子どもの成長にとって大事なことです。
でも、ちょっと立ち止まって考えてほしいのです。
叱ること、ほめること――それだけで、本当に子どもは自立していけるでしょうか?
もしかすると、叱られないために働く。ほめるためにがんばる。
そんな風に、子どもが「他人の評価」に振り回されてしまうとしたら…?
この記事では、教育の目標である「自立」という観点から、あえて「ほめない」「叱らない」とう視点で子どもの関わり方を見直してみたいと思います。
- 子どもとの関わり方を見直したい
- 子どもの自立を促したいと考えている
- 一般的な「ほめて伸ばす」教育に違和感を感じる
教育の目的は「自立」


教育の本来の目的は、子どもが自分の力で生きていけるようになること――つまり、「自立」です。
自立とは、自分で考え、行動し、責任を持てるようになることです。
では、その自立を育てるために必要な関係性とはどのようなものでしょうか?
「叱る人」――「叱られる人」
「ほめる人」――「ほめられる人」
こうした関係には、明確な上下があります。
そして、この上下関係は依存関係を生み出しやすいということを意識する必要があります。
上下関係がもたらすもの


上下関係ができることによって、どのように自立を妨げてしまうのか、掘り下げて説明します。
叱ることの影響
叱るという行為は、一見「悪いことを教えるための指導」に見えます。
しかし、そこには無意識のうちに次のような関係が生まれます。
叱る人【上位】 ⇔ 叱られる人【下位】
叱られた子どもは「認めてもらうために」行動するようになる。
時に、叱られた怒りや不満から、反発や復讐心を生むこともある。
つまり、自分の頭で考えて行動するのではなく、「叱られないために」行動するようになるのです。
ほめることの影響
一方で、ほめることも一見すると良さそうに見えます。 でも、ここにも問題があります。
ほめられたいから子どもは頑張る。
ほめてくれる人がいないと頑張れなくなる。
他者からの評価に依存することにつながる。
つまり、自分の内側の価値観ではなく、「外からの評価」によって行動が左右されてしまうのです。
他者と比べて勝つことが価値という思い込み
叱られたくないから頑張る。
ほめられたいから努力する。
この仕組みは、結果として他者と比べて勝つことが価値だという思い込みを生みます。
そして、その先には、こんな考え方が潜んでいます。
- 周りは「競争相手」=敵
- 負けたくない、評価されたい
- 間違えたらダメ、弱さは見せられない
これでは、子どもが自立するどころか、他人と比較して自分を見失っていくことにもなりかねません。
教師も子どもも関係ない「横の関係」を目指そう
ここまで聞いてどんなことを感じましたか?



ほめてもだめ、叱ってもダメ。「じゃあどうしたらいいの?」って思いません?
ここからは、どうしたらよいのかについて話していきます。
大切なことは、教師という立場であっても、子供と「横の関係」であろうとする態度を持つことです。
「横の関係」とは、すべての人は対等であり、他者と助け合ったり、協力しあったりする関係のことです。
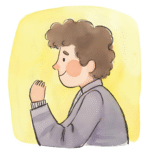
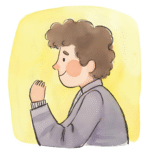
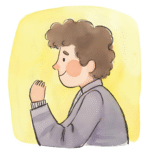
ちょっと待って!「横の関係」って子どもと友達みたいになれってこと?
このように感じた人もいるかもしれません。
たしかに、教育の現場では、子どもに“なめられてしまう”ことへの不安もあると思います。
学級経営のために、ある程度毅然とした態度が必要な場面もあるのは事実です。
しかし、本当に子どもに自立してほしいと願うのであれば、教師がまず「横の関係」作ろうとすることが大切です。
- 周りは仲間であって、敵ではないこと。
- ともに考え、ともに成長する関係が大切であること。
- 互いに貢献し合える存在であること。
こうした感覚を、子どもが自然に持てるような関わり方こそが、「依存」ではなく「自立」につながっていくのです。
具体的にどのようにしたらいいの?


では具体的にどうしたらいいかについて「叱りたい」「ほめたい」場面を想定しながら3つほど示します。
正しいことを教える、一緒に考える
子どもなので当然間違ったことをすることはあります。大切なのはその時の関わり方です。
たとえば、友達に暴力をふるってしまった子どもがいたとします。
このような場面では、頭ごなしに叱るのではなくまずその子の気持ちや背景をしっかりと聴き取ることが大切です。そして「暴力は何があろうと絶対に許されない」ということを教える必要があります。
ここで大事なのは、行動は正すけど、子どもそのものは否定をしないこと
たとえば、こう問いかけてもいいかもしれません。



○○さん、次に同じようなことがあった時に、どうしたらいいと思う?
または、



今回のことをきっかけににして変わっていけるように、一緒に頑張ろう。
このように、正しさを伝えながらも、対等な立場で“次”を考える姿勢が、子どもの中に「自分でどうするか」を考える種を育てていきます。
「評価」ではなく「事実」「共感」「感謝」
たとえば掃除の時間、子どもがトイレをとてもきれいに掃除してくれたとします。
そんなとき、
- 「上手に掃除できたね」
- 「えらいね!」
などと、つい言いたくなりますよね。
もちろん、声をかけること自体は大切です。
でもこういった言葉は無意識に「評価」が含まれていることがあります。
ちょっと考えてほしいのです。
「それ、友達にも同じように言えますか?」
もし、自分と同じ年齢の友人がトイレ掃除をがんばっていたとき、同じように「えらいね」「上手だね」と言うでしょうか?
おそらく、「ありがとう」「助かったよ」など、もっと対等な言葉になるのではないでしょうか。
例えば、このように言うとどうでしょう?



汚れがめちゃ落ちている!大変やったやろう?ありがとうね。
- 汚れがめちゃ落ちている = 事実
- 大変やったやろう = 共感
- ありがとうね = 感謝
子どもと関わるときも、こうした評価ではなく「事実」「共感」「感謝」で伝える姿勢が、
上下関係ではなく“横の関係”を築くための大切な言葉の使い方になります。
コントローラーを手放す
普通の授業でも「横の関係」を意識することは大切です。
僕には、学校でよく使う口癖があります。



みんな(〇〇さん)はどう思う?
ある日の国語の授業。
詩の単元で、僕はこのように説明しました。
「教科書に載っている詩を読んで、工夫されているところを見つけよう。
それをヒントに、自分たちでも詩を作ってみよう。」
その後、「みんなはどう思う?」と問いかけました。
すると、1人の子がこう言いました。



まず自分たちで詩を作ってみたい。その後、教科書の詩と比べてみたい。
この言葉に、クラスでは「いいね!」という声があふれました。
授業には時間の制限があります。
どうしても教師が主導権を持って、計画通りに進めたくなる場面もあります。
でも、そんな中でも、「授業のコントローラー」を子どもに少しずつ渡していくことは可能です。
子どもの声に耳を傾け、ともに考えながら授業を作っていく。
それこそが、「横の関係」の実践につながっていくのではないでしょうか。
おわりに
ここまで、「ほめない・叱らない」関わり方、
そして「横の関係」を大切にする教育の姿勢についてお話ししてきました。
大切なのは、子どもをコントロールしようとするのではなく、
一人の人間として対等に向き合い、ともに考え、ともに成長すること。
もちろん、私自身も、いつもうまくできるわけではありません。
怒ってしまうこともあるし、つい上から目線でほめてしまうこともあります。
でもそれでいいのだと思います。
完璧を目指すのではなく、「意識を変えること」からすべては始まるのです。
たとえば、今日から子どもへの声かけを
「評価」ではなく「感謝」や「共感」に変えてみる。
そんな小さな一歩でも、きっと何かが変わり始めるはずです。
あなたの教育の現場が、
子どもと大人が共に育ちあえるあたたかい場所でありますように。
ここまで、読んでくださってありがとうございました。
-1.png)
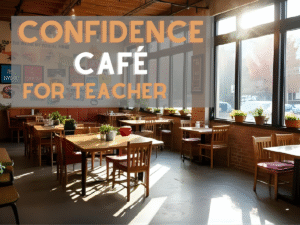
コメント